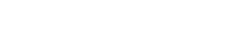日本刀刀身各部分の解説(下)
前回に引き続き、日本刀刀身各部分の解説をいたします。
今回は「樋及び彫刻」から見ていきましょう。
六、 樋及び彫刻
樋とは、図20の如く、刀身の「鎬地」の部分が、溝になっているところをいうのでありますが、俗にこれを「血流」などといいます。.jpg) 樋は、大体最初は刀工の信仰心の発露から起こったものと思われます。図21の棒樋などは、不動の利剣をかたどったものでありましょう。然るに後世に至りましては、刀身の重量の軽減のために彫ったり、実用上斬れ味をよくするために彫ったり、あるいは装飾として彫ったりするようになったのであります。
樋は、大体最初は刀工の信仰心の発露から起こったものと思われます。図21の棒樋などは、不動の利剣をかたどったものでありましょう。然るに後世に至りましては、刀身の重量の軽減のために彫ったり、実用上斬れ味をよくするために彫ったり、あるいは装飾として彫ったりするようになったのであります。
樋には下の種類があります。~(29).jpg) その他は略す。
その他は略す。
図21の棒樋には下の如き彫り方があります。~(35).jpg)
彫刻とは、刀身に、鏨を使って種々な文字や絵画などを彫ったものであります。
彫刻も、樋と同様、刀匠自身の信仰心あるいはその注文主の信仰心より、その多くは、神仏の称号または尊体などを彫ったものでありますが、後世は、神仏その他人物、花木、動物などを装飾として彫刻するようになりました。
上古時代には、随分精巧なものが、しかも象嵌などをした彫刻あるものを、折々見る事があります。
日本刀となりました古い頃には彫刻はあまり見ませんが、平安朝の中頃のものには、古雅なごく簡単な彫刻などを見る事があります。
鎌倉朝の中頃からは、彫刻が流行しはじめました。
元寇の乱から、南北朝期にかけまして、急激に彫刻が多くなったのであります。神仏の称号、仏像などで、多く世相一般の、それもおもに日蓮宗などが中心となって、宗教心が熾烈になりました事が、裏書される訳であります。
足利の室町時代から、戦国時代にかけましても、益々彫刻は流行いたしましたが、この時代は、仕入物と注文打との区別が甚だしくなりましたので、実用一方に使用されました仕入物にはあまり彫刻はありませんが、愛蔵するために入念に鍛えさせました所謂注文打には、彫刻は多いのであります。
豊臣、徳川時代になりましては、意匠も濃厚に絵画的になりましたが、この頃は刀工自身の彫刻よりは、別に彫刻師の彫ったものが多いのであります。
幕末においては、益々この傾向が甚だしかったのであります。
彫刻の種類には種々ありますが、その多く世にありますものを掲げますと~(43).jpg)
七、 焼刃・刃文
焼刃とは、刀身の刃の方の部分に、白い所があります。それを焼刃といいます。その焼刃の形が種に模様化して、図44の如く文になっておりますから、これを刃文といいます。.jpg) これは、強靭な鋼鉄を、より以上に強くする事によりまして、斬れ味をよくするために工夫されたものであります。
これは、強靭な鋼鉄を、より以上に強くする事によりまして、斬れ味をよくするために工夫されたものであります。
その焼き入れ方法については、鍛錬の方で説明されましょう。
この焼刃を構成しておりますものに、沸と匂というものがあります。
その沸と匂とで、種々にこうせいされましたのが、即ち刃文であります。
さらば、沸とはどんなものかと申しますと、焼のあります部分、殊に焼刃と地鉄との境に最も細かく、よく光る粒々が沢山に見えます。丁度銀砂子を撒いたような粒であります。地の方にも現れておりますが、焼刃の方がよく判ります。焼刃の方にありますのを「刃沸」、地の方にありますのを「地沸」といいます。
沸を見ますには、まず自分の体を暗い方に向けまして、光線を背後から探り、刀身を立ててこれに光線を反射させて見るのです。
その沸で刃文を構成しておりますのを「沸本位の焼刃」といいます。.jpg)
匂とは、沸の粒が極度に細かくなり、肉眼では沸の粒が見えなくなりまして、ただ焼刃の頭に焼刃の形なりに、細い線となって見えるものであります。それでありますから、焼刃と地鉄との境界線ともなっているのであります。丁度払暁太陽が東の空に今や上らんとする、地平線上の色合のようなものであります。その線の太いのを、匂が深いといい、その線が細いのを、匂が浅いといいます。
匂を見ますには、沸を見ますのとは反対に自分の体を明るい方に向けて、刀身を斜めにして透して見るのです。
匂で構成しております刃文を「匂本位の焼刃」といいます。.jpg) その沸や匂から起こりました、一種の働きに砂流、金筋、稲妻、打のけ、掃掛、地景、湯走、地映りその他のものがあります。
その沸や匂から起こりました、一種の働きに砂流、金筋、稲妻、打のけ、掃掛、地景、湯走、地映りその他のものがあります。
刃文には、沢山の種類がありますが、その多く見るものを掲げますと~(67).jpg)
八、 帽子
帽子とは、切先の中の焼刃の事をいうのであります。下の如き種類が多くあります。~(76).jpg)
九、 地鉄肌
地鉄とは、刀身を構成している所の、鋼鉄の総称であります。但し、鑑定上におきましては、刀身の中で焼刃以外の黒く見える部分を地鉄といっております。よく鍛えて最も密なものをよい地鉄といいます。荒い粗雑な地鉄、柔らかな地鉄、強い地鉄などがあります。
地方的に分けますと、五畿内方面の地鉄が最も細かく、中国九州方面の地鉄がこれに次ぎ、関東方面は荒くなります。殊に日本海に面しました、即ち裏日本方面は強いのであります。
肌とは、鍛錬の場合に、槌で叩き折り返しては叩き延しました折目である、というのが最も簡単な説明方法であります。でありますから、これを拡大して見ますれば、肌には、微かな間隔があるのであります。
即ち、刀身の表面に、丁度板の目の様で白く現れておりまして、刀工の鍛錬法によって、下の種類があります。~(81).jpg)
十、 茎
茎とは、図82の如く、刀身の元の方で柄に入っている部分をいいます。刀工は自分の作名をこの所に刻み込んで置きます。.jpg) 刀身の上部は、錆びないように研ぎを掛けて、綺麗にしておかねばなりませんが、茎はそれと全く反対に刀工が鍛え上げた時のそのままの状態でなくてはならないのであります。錆の色に五百年六百年の時代が古色そのままにあるのが最も尊ばれるのでありまして、無銘のものなどはその古色の錆具合によって、その時代が推定されるのであります。
刀身の上部は、錆びないように研ぎを掛けて、綺麗にしておかねばなりませんが、茎はそれと全く反対に刀工が鍛え上げた時のそのままの状態でなくてはならないのであります。錆の色に五百年六百年の時代が古色そのままにあるのが最も尊ばれるのでありまして、無銘のものなどはその古色の錆具合によって、その時代が推定されるのであります。
古い時代の太刀の茎は、細くて長いのでありますけれども、足利時代以降のものは太くて短いものが多いのであります。
鎌倉末期から、南北朝時代の太刀は、寸法が長いので、足利時代以降、佩用法の変化によりまして寸法を短く切り詰められました。これを「大磨上」茎と称しております。茎には左の種類が多くあります。~(86).jpg) 茎に、刀工が鑢目を残して置きます。その種類には、槌目、せんすき、切、勝手下がり、勝手上がり、筋違、鷹羽、檜垣などが多くあります。
茎に、刀工が鑢目を残して置きます。その種類には、槌目、せんすき、切、勝手下がり、勝手上がり、筋違、鷹羽、檜垣などが多くあります。
徳川期の刀工は図87の如く化粧鑢を使って、鏟目を最も正しく残しております。.jpg)
(NHK「ラヂオ・テキスト 刀剣講座」より)