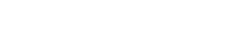日本刀の形態研究 第四章 日本刀の発展について 第二節 一文字時代(古刀後期)‐二
日本刀の形態研究(七)-六
日本刀の形態研究 第四章 日本刀の発展について
第二節 一文字時代(古刀後期)-二
○一文字時代の作風
造込み=一文字時代も造込みに於いては、前代とあまり異なるところはなく、即ち寸法は二尺六七寸、身巾相当に広いというのが普通であったろうと思われます。しかし時代降ると共に巾広の太刀が現れてくるのは、次第に丁子の焼巾広い所謂大丁子の作品が生まれたためでしょう。そうなると自然重量を増すので、これを防ぐため樋が掻かれます。樋は俗に言う血流しでも装飾でもなく、その最初の目的は専ら重量を減らす事にあったと考えられます。その様な次第ですから古い刀は樋ある事によってのみ見ても身巾重量の相当にあった事が考えられます。注文者の意向によって多少の差はありますが原則としてそうあるべきで、今日樋のある姿のよい細身の刀を見るのは研減りの結果か、後世(慶長頃より)に至って形体の美観を重んじて殊更なされたものであると思います。樋は掻流しが古い形式であり次いで角止が行われたと思われます。古備前時代の古い作品には概して樋は掻通しを施されていると思います。刀は原則として巾広く重ね薄く造るのが切れるという条件に叶うのです。そして平造直刀より進化して反りのある鎬造りへ次第に移ったと考える時、樋のある刀は何となく原始的な姿から遠い感じがします。なので樋のかかれる事は一文字時代から弘安頃迄が最も顕著であったと思います。
地鉄=地鉄板目は古備前同様ですが、次第に鍛錬の進歩があり鉄と鉄との密着が細かくなります。即ち板目ながら従来の板目と異なり、それ等は杢目に変化する傾向を含むものです。
刃文=一口に一文字丁子といいましても様々な相異があります。初祖則宗や信房などにあっては丁子乱ともいうべく所々に沸崩れを交え焼巾の広狭が著しく、中には鎬地や棟へかけて焼きの飛び散ったものさえ見受けられます。これは匂出来の丁子を焼くという技術においては素朴的といえます。これが洗練されるならば一文字吉房に見るあの絢爛たる匂出来の大丁子となります。しかしまた一方には古備前風の小乱より進化したと思われる小丁子作品があり、これは焼巾の広狭の著しからぬものです。小丁子は多く刀の姿優しいものに見られますが、概して古い傾向のものという事が出来ます。しかしこれ等は流派別にしても個々の刀工にしても一貫した作風としてではなく相交錯していますのでこれのみにて時代の先後を決することは適当ではありませんが、小丁子、丁子乱が時代の降るにつれて次第に大丁子に向かう傾向がある事だけはいえます。
この大丁子に向かう勢は今日我々が精巧な研磨を経て之を見る場合の如く匂いの美観を求める心ではなく鋭利な切断力の表現にあったのでしょう。美しい感じよりも切れそうな威力を示す事こそ丁子刃の本義であったと思います。なのでかかる勢の赴く所必然的に大丁子作品へ向かうことは考えられるべき理です。
丁子作品の基礎をなした則宗、信房等の丁子乱れは古備前の小乱、直足入り、小丁子からは確かに異色ある作風です。その時代既に焼巾統一されているのに再びまた広狭著しい作風を見ることは淬刃の操作からいえば調和を失うものというべきですが、しかし新たな変化を狙った点進歩的で、この傾向が遂に一文字一派において完成され吉房等の見事な丁子となった事からして、彼らが系譜的にのみでなく眞に一文字の鼻祖たるべき意義があるとしなくてはなりません。またその帽子の作風をみると乱れ込みが多く、末期の吉房、助眞の大丸、小丸の整然たるに比して時代の古さを窺い得るものです。こうして文永の頃迄丁子刃全盛の時代となるのですが、この中心をなしたのは一文字鍛冶でして、彼らの念頭に宿りし父祖の御番鍛冶たる栄光は遂に一文字丁子をして特異の存在たらしめた理念であったと考えなくてはなりません。
茎=茎の型においては古備前時代と大差ないのですが、雉子股のものが多くなるのが目立ってきます。この中にはやはり同時代のものと後世のものとがありますが、何れも刀工自身によりなされたのではなく拵の必要から刃棟を磨り取ったものです。茎に一の字を切る事により一文字派の名前の由来するところとされていますが、この一の意味に付いては学者により種々の解説がなされています。タガネにて切った一の字は極めて無雑作なものがあります。この一の文字の下に、個銘を切ったものがありますが、これらは研究を要するものが多いようです。
銘字はだいたい大きい二字銘、大胆にのびのび切られていることは古備前時代同様ですが、末期に至ると幾分萎縮しているような感じを持つものがあります。これ等は文字の形を造るという意識によるものでしょうか。一文字吉用などはこの例といえます。総じて作品の残るもの豊富な為か同じ作者の銘をならべて見ると、銘字の進歩を物語る変換が窺われるのは極めて興味深い事柄です。
(「日本刀要覧」より)