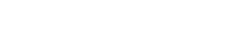日本刀の形態研究 第四章 日本刀の発展について 第二節 一文字時代(古刀後期)‐三
日本刀の形態研究(七)-七
日本刀の形態研究 第四章 日本刀の発展について
第二節 一文字時代(古刀後期)-三
○沸と匂いについて
小乱といい丁子刃といいそれ等は地鉄と刃界に現れる匂や沸によって形成される紋様ですから、我々はそれ等沸匂の出てくる根拠についての知識を持たなくてはなりません。沸というのは肉眼で見る時焼刃界における粉粒の如き白色のツブツブのものであり、匂は模糊として白く霞のたなびいた如くなっているものです。これ等は刀を少し見慣れた人々は実物を見て直ちにそれと分かるものですが、言葉のみを以ては中々適切な表現が出来かねるものです。しかし何れも溶融状態にある鋼の炭化鉄が冷却によって凝固結晶することにより生ずるもので、この際大きいものを沸、小さいものを匂と称するのです。古来匂沸の論議はこれらを良刀の必須条件としていたく尊重する人々と反対に無用のものと排除する一派があります。しかし我々は刀工の努力は鍛錬によって良識を得る事にあると考えるものですから、それ等を殊更珍重する者ではありません。ただ沸匂の本質を知りこれに通ずる事は刃鋼の硬軟地鉄の性質等に関して我々が鑑刀の場合極めて必要な知識ですから、その事をよく念頭に置くべきです。
含有炭素量の多少がいかに沸匂に影響するかというと
(一)硬き鋼にして、即ち1.0,0.9,0.8の炭素量を有するものを700度に熱する時は既に立派な匂が出来、750度以上に及べば沸が発生する。(実際は硬い鋼は沸が出来やすく、匂は出来にくいものでこの場合刃は黒いものです)
(二)頃合いの鋼即ち炭素量0.5,0.6,0.7位のものを750度で一定時間熱した場合に初めて最良の沸匂が美麗に発現する(硬鋼に出来るものよりも冴えないものがある)
(三)軟らかい鋼即ち炭素量0.4,0.5の鋼は匂は発生するも沸はつきにくく、800度以上に一定時間熱する時は炭素脱出して鉄が駄目になる。(堀井俊秀閲、佐藤富太郎著日本刀の秘奥)
上三條についての説明は含有炭素量の多少と匂沸の発現との関係にてこの事は柴田果氏の証明によってもよく窺われます。
(一)鉄の炭素量が多いと匂になる。即ち薄火で焼きが入るからです。
(二)火が薄いと弱い匂になる。炭素が不足すると沸になる。
上の説明は一見佐藤氏と反対の如くですが、灼熱温度を中心にいっているからで、薄火でとある点に注意すれば結局同様の事実を述べられているのです。従って用いる材料としては千草鉄(0.7-0.8)より出羽鉄(0.8-1.0)の方が沸がつき易いのです。(高橋貞次氏談)
また沸匂は灼熱温度との相関係によって種々に発生するものです、加熱においてのみ発生するのでなく、急激な冷却の際に結晶硬化するので、自ら冷却温度に関係するところが甚大です。
(一)硬鉄を700度の低温で熱しても摂氏67度内外の水で冷却する時は沸となり、7、80度の高温中に冷却する時は匂となるものです。
(二)頃合いの鋼も上の場合と同様の影響を受けます。
(三)軟らかい鋼の冷却は78度位の低温あるいは20度位迄には焼入れが出来ても50度以上の高温では焼きの入らない事です。
この様に匂沸の発生と加熱及び冷却温度の関係はなかなか複雑で、上は極めて大略述べただけですが、詳細に説明するならば同一の鋼を同温度に熱し、ただたんに冷却温度が異なるだけでも下の如く変化を起こすのです。
冷却の推理
(一)摂氏10度の水にて最大なる沸が発生すると仮定して。
(二)20度の水で冷却すると小沸が出来。
(三)30度の水では冴えたる匂が発生し。
(四)40度では薄くしかも沈んだ匂、俗に言う眠い匂が出来る。
という具合にて同一炭素量を有する鋼を同一温度に加熱しても冷却温度の相違で大別してさえ四種の変化を喚起致しますからこれが炭素含有量不等にして加熱温度の不等の場合、高低不等の温度を有する水を以て冷却する時はその変化たるや実に幾十幾百種の硬度を異にするものが出来るのです。(日本刀の秘奥)
その様にして焼入れに際し必然的に生ずるものが沸匂ですから、刀工の努力は専ら鍛錬によって適当の硬度を有する良鉄を作り焼入れによって刃鋼を形成する事にかかっています。それが沸や匂に重点を置く事になると刀剣製作の上からは自然邪道に陥る様になるのです。平和の時代にあってはかかる過誤を犯したものが少なく水心子正秀のいう匂沸無用論はかかる誤りを戒めたものと考える事が出来ると思います。また鍛錬の意味は炭素量を適当にし鉄に含まれたる不純物を除くにありますから、これが焼入れに及ぼす影響は最重大です。刀工の修行は鍛錬と焼入れにあり、鍛錬宜しからざれば意のままに、焼刃を作る事を得ず、たとえ表面的に出来得た如く見えても刃鋼の硬度、弾力において適当ならず実用に耐えないという結果になります。鍛錬という点についてのみ着目すれば匂沸は如何というに鍛錬回数多ければ匂となり、少ない時は沸となるので、相州伝の如きは鍛錬回数少ないものであるといえます。(柴田果氏談)しかし一定の度合いを越してまで鍛錬すると鉄が駄目になって焼入れが出来ない事になるのです。
次に匂沸が影響せられるのは焼き入れに用いる土取りです。焼土なるものは粘土末木炭末、荒砥石末を以てよく練り合わせに用いるものですが、これが刀身灼熱の際よく密着して炭素の飛散を防ぐのです。冷却に際してはこの焼土が現状のままでみる事は難しくその変化作用に応じて焼刃と刃文を生ずるのです。この際の変化に付いて柴田果氏はその深い経験を基礎に次の如く要約して下さいました。
○火上る(土の中まで界を越えて焼が入ったもの)は沸となる、この際適当に行くと小沸となる。
○土が薄いと業沸となるようである。
○土を厚くつけて火強く焼き小沸をつけたもの(沸はあまり冴えない)をアヒを取る(火を戻す)と沸がさえて来る。
以上簡単ながら沸匂の出来る原則的な条件について述べてきたところによりますと、鉄の含有炭素量、灼熱温度、冷却温度、土取等全ての相関において沸のつき得る条件は匂のそれに比べて広汎である事が分かります。匂の条件は極めて限られた瞬間でこの状態が少しでも度を過ごす時は沸となり焼が入らなくなる(鉄が駄目になって)のです。
その様な次第で匂本位の一文字丁子の製作が今日極めて困難とされる所以であり、これに対し相州伝が比較的易しいと考えられる因由です。勿論よい作品をなす事は何伝たるを不問困難なる業ですが、上の理由を考えるならば匂出来の丁子の出現する瞬間が極めて狭い範囲にあり、刃文を台末も崩す事が出来ないという点で一文字伝丁子が最も難しい技術に属すると現代刀工の立場からいわれえるのです。高橋貞次氏も「相州伝風の大乱刃よりも備前伝風の丁子刃の方が難しい。各々得意にもよりますが、一口にいえば相伝は火取、土取も無雑作に且大胆にやった方が変化して面白い出来となる事が多いようですが、備前伝丁子刃の匂足が深く重花になった様な出来は土取火取も少しの油断も出来ず、火ムラなく冷水中にて淬刃する事になるのでこの方は刃味もよく刀匠として困難な業です。」と言っておられますがよく這般の事情を物語っている味わうべき言葉と思います。
焼刃、刃文の出来ることは今まで我々が分析的に考えたような原因が単純に重なって結果となるのではなく、それ等無数に複雑に錯綜して極めて微妙な原因と化学的変化の過程に参興するものですから、誠に神秘な業とも見るべきものです。古来刀鍛冶の焼入れ作業等に種々の伝説が託されているのも複雑な現象を取扱うからです。現代の科学研究といえどもこれ等につけて知悉されたものでもなく将来益々着実に研究されるべきであり刀匠の技術を徒らに人力の測り得るべきところに非ずとして学問的研究を退けるのは当を得た態度といえません。また科学的知識といえども今日万全を知りえたのではなく、刀工の古くより伝えられた経験を無視するならばこれも認識不足です。古来の技術を化学的知識によって解明し、将来の飛躍にまで高める事こそ現代人のなすべきところであるといわなくてはなりません。
話が少し脇道にそれましたが、次に種々に作られた沸と匂とは何れが硬いかという問題ですが、それに於いても炭素量、加熱温度、冷却の三方面について観察されるのです。即ち炭素量に於いては多いものに生じた沸は少ないものに生じたものより硬く、冷却温度は冷たい水にて急激に冷却したもの程硬いのです。また加熱温度は高いもの程硬いという事になっています。而して一般に沸は匂より硬いと考えられるものですが炭素量、加熱温度、冷却その他諸種の条件が混合すると出来た沸匂の硬度も非常に複雑になり沸必ずしも匂より硬くないという事さえ起こりえるのです。
かくして刀匠の努力は良鉄を鍛錬によりて得ると共に最後の焼入れにおいてその成果を得るものですから、始めから終わりまで少しの油断もできずその努力は並大抵ではありません。これ等全ての知識を研究と体験によって知悉し思うままに再現しえる人々こそ名工と称すべきであります。また単に知識のみならず日本刀の作者は高遇卓越の精神保持者にして初めてよい作品を生み得るのである事も忘れてはなりません。
○則宗(一文字)「承元ー備前」
作品太刀多く刃長二尺六七寸、地鉄板目締る、刃文丁子沸つきのたれ心になるもので丁子乱ともいうべき刃文、帽子は沸崩れまたは乱込み作風全体が丁子刃の未完成なるを覚えこの点からも一文字の祖に適わしい。
○信房(一文字)「元暦ー備前」
作品太刀、刃文丁子を焼くものもあるが、小乱作品もある焼巾広狭あり則宗に似る、帽子は乱込み、信房なる刀工は古備前にもありとされるが、作風の小乱的なるものを古備前とし丁子風たるを一文字とした後世鑑定家の見解ではないか。
○助宗(一文字)「承元ー備前」
作品太刀多く樋もある、刃文小乱又は丁子。
○守次(古青江)「仁平ー備中」
太刀多く、樋掻き通しになるものがある。刃文小乱、帽子乱込み作風は古備前に似るも時代的には一文字初期則宗等と同列にあるものと思われる。
○助包(一文字)「承元ー備前」
作品太刀幾分巾より、掻き通し樋が多い。地鉄小板目、刃文直に小乱交じり沸崩れまたは丁子刃鮮明なもの。
○則房(一文字)「建長ー備前」
作品太刀多く掻き通し樋もある。地鉄板目刃文小丁子焼巾広狭あり、また丁子刃にして丁子の頭激しく尖心になるものを見る。
○一文字「承元ー備前」
茎に一文字を切りたるもの作者は誰と指定出来難い。
○助眞(一文字)「文永ー備前」
作品太刀二尺五六寸巾広のもの多く、掻き通し樋あり、地鉄小板目締る。匂または小沸出来の丁子、大丁子刃文は鮮明丁子頭焼深いものが多い。帽子は小丸の至大丸。
○吉房(一文字)「建治ー備前」
作品太刀刃長二尺五六寸位のものが多く、掻き通し樋もある。吉房の丁子、大丁子は何れも小沸または匂出来にて極めて鮮明なる刃文であり、帽子小丸の至大丸整然として卓越する手腕を窺う事ができる、従って時代的にも信房等に比べると後に属する事が分かる。
○國安(粟田口)「正治ー山城」
直小乱入りまたは小丁子沸つく、帽子大丸または乱込み一文字末期の刀工と同列にあると思われる。
(「日本刀要覧」より)